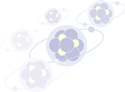|
第4回 コーディネーター会合 要約
2003年3月5日~7日 沖縄県那覇市
FNCA9カ国のコーディネーターが集まり第4回 コーディネ-ター会合が平成15年3月5日~7日に沖縄で稲嶺知事および大村大臣政務官の挨拶で開会、「目に見える成果を目指す」という目的に向けて実質的な水平協力を実施するための議論が行われた。
 |
| 第4回 FNCA コーディネーター会合風景 |
1. 2002 年度における活動とその成果報告
(1) 医療分野2つのプロジェクト
① PZC法Tc-99mジェネレーターの実用化
中国の張華祝主席(国家原子力能機構)は中国ですでに 1000の病院で放射線医療が行われていると述べている。 FNCA参加国はいづれも核医学に不可欠な Tc-99mを輸入しており高い対価を支払っている。したがって自国が所有する研究炉で製造することができればそれが国益に合っている。研究炉でn‐γ反応で作った Mo‐99 は比キューリーが低いので、 Polyzilconium Compound (PZC)に吸着させて、濃縮させる方式が原研と (株) 化研によって開発された。プロジェクトではこれを実用化技術として完成させ利用することを目標にしている。マニュアル法による公開実験がインドネシアと日本の協力で今年1月のワークショップで実現した。本年12月には自動化されたカラム製造試験装置をインドネシアに設置、公開共同実験に利用する。
②「子宮頚がん」放射線治療 - 5年生存率54%を達成-
生活環境が良くないアジアの途上国では女性の死亡原因の1~2位を占めるのが「子宮頚がん」である。これに対する放射線治療を効果的に行うため、「標準的治療法」による臨床試験を 210 例について FNCA8 カ国で実施した。 5 年後生存率 53.7 %、局所制御率 81.5 %という非常に良好な成績が報告された。この「治療手順書」がガイドブックとして英語で出版され、 FNCA 各国は勿論、 IAEA のワークショップでも利用されている。今後の計画は「多分割加速照射法」による治療成績の一層の向上、治療の品質保証と品質管理( QA/QC )の向上を図ることである。「多分割加速照射法」についてはすでに 102 例の登録がある、臨床試験は進行中で相当に良い成績が得られている。
| 治療前 |
|
治療後 |
 |
|
 |
| 子宮頚がん MRI 画像 |
(2)農業分野で「生産性が高く、環境にやさしい農業」を目指して2つのプロジェクトが進行中
①「バイオ肥料」のフィールドデモンストレーション
大豆などマメ類の食品は途上国の人々にとって、重要なたんぱく源である。マメ科植物の根に共生し、空気中の窒素を固定する根粒菌は収穫を高める。化学窒素肥料は価格も高く、地下水など環境の汚染を引き起こすという問題がある。
FNCA のプロジェクトとしてライゾビアなどの微生物を接種して収穫を高める「バイオ肥料」の普及が行われている。 N - 15 を利用した固定化率の測定法による最適微生物の選定、照射殺菌による微生物培地の製造が進められている。 2002 年はとくにバイオ肥料の効果を具体的に示すためのフィ-ルドでのデモンストレーションを計画した。 2003 年度各国で実施する。これが「バイオ肥料」普及の契機になることを目指している。
②品種改良は耐乾燥性「大豆」と「ソルガム」に重点
雨が少なく、乾燥した土地の多いアジア諸国では、乾燥に強い品種が必要で、とくに重要な食品である「こうりゃん」と「大豆」についてニーズが高いので FNCA プロジェクトとして 2002 年から開始、すでに中国、インドネシア、フィリッピン、ベトナムの間で変異種の交換が始まっている。 3 年後の成果が期待される。

インドネシアでの「ソルガム」の品種改良研究 |
(3)原子力の安全
FNCA では原子力安全を向上させるために、2つのプロジェクトを進めている
①原子力安全文化
FNCA では各国が運転している研究炉での安全確保のためにその規制体制などについて検討を行ってきた。 2001 年の WS で「研究炉に関わる安全文化」を
1 ヶ国・1研究炉についてピアレビューすることが決まり、第 1 回が 2002 年にベトナムダラトの研究炉で行われたことは注目に値する。このピアレビューでは
12 の模範的な実践を誉め、安全向上のため 16 の勧告をしている。これらが今後の一層の安確保に役立つと期待される。

ベトナム研究炉安全文化のピアレビュー |
② 放射性廃棄物の安全管理 -使用済線源管理は成功裡に終了-
各国の RWM (放射性廃棄物管理)の現状を取りまとめたレポートが完成し、出版された。これは各国の RWM の改善に大いに参考になる。タイの使用済み線源による事故を繰り返さないために 2002 年まで重点的に行なった「使用済線源の安全管理タスクホース」はタイ、フィリッピン、韓国、インドネシアで実施し、いくつかの具体的改善勧告が行われ、各国にとって有益な成果となった。 2003 年からはテノルム( Technology Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material )の安全管理活動を重点的に進める。
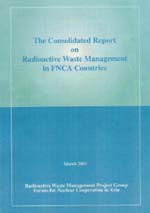
放射性棄物管理の統合報告書 |
(4)原子力広報
2002 年は 8 カ国 8800 人の高校生対象に「放射線とその利用についての合同意識調査」が実施され、大きな国際的調査として注目される。現在その成果を細かく分析している。その結果はいづれ別に報告したい。アジアのスピーカーズビューロー活動ではマレーシアの原子力国際会議( INCO2 )に日本から 3 名を派遣し特別講演を行った。

バンコクでアンケート調査に参加する高校生 |
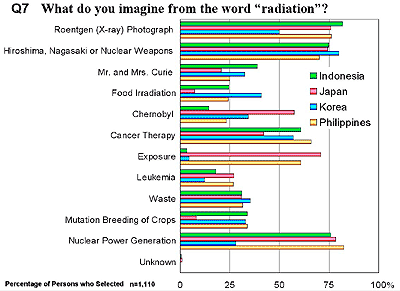
アンケートの一例 |
(5)人材養成
「持続可能な原子力」にとっては次世代に向けて人材の確保が不可欠である。 FNCA では「放射線安全」と「原子炉物理演習」について英文テキストを配布してきた。一方新たに、各国の分野別人材の充足度などについての合同調査を開始した。この調査は 2004 年に解析を含め完成させる。また、 FNCA 大臣会合でも議論になった「アジア原子力教育・訓練ネットワーク」構想は韓国中心に進行中で 5 月に IAEA の会議が韓国で開催される。日本の役割を検討することが重要である。
(6)研究炉と電子加速器
原子力利用を推進する2つの重要な手段として、研究炉と加速器がある。両者とも日本ではに原研を中心に進めており、各国の意欲も高い。
①研究炉利用
プロジェクトとして、 a. 放射化分析( NAA ) b. 中性子散乱 c . テクネシウムジェネレーターの3つがある。 NAA は大気中の浮遊塵の採取と NAA 共同分析が動き出し、解析手法として Ko 法の改善・普及に重点をおいている。 Ko 法では中国・ベトナムのソフトが重要な役割を果たしている。成果の活用について各国での環境政策担当省との連携の重要性が指摘されている。
①電子加速器利用
低コストの低エネルギー加速器システムを工夫して、液体、フィルム、粒子、粉体状固体に適用する。液体についてはすでに 2002 年 12 月日本でデモスト-ションを実施した。 2003 年はマレーシアでフィルム状材料に適用しハイドロゲルを合成するデモストレーションを実施する計画である。
2. 「パートナーシップの理念」を根付かせる - FNCA 運営の改善-
以上、述べたように 2002年度、「目に見える成果」を目指して各国の活動が動いている。これからの開発・発展が必要な途上国においては社会・経済的効果が求められていることが確認された。
プロジェクト活動は参加国が自国予算で原子力研究機関・大学を活用して推進している。大臣がトップに居り、 FNCA 本会合にて政策を議論しているのであるから、国レベルの参加がさらに強化されるべきで、日本、オーストリアに加えて途上国がホストするプロジェクトが発足することが期待されている。また、この議題では成果の利用者(病院、農業者、研究機関など)との連携を強化すべきことが合意された。
3. 新プロジェクト「アジアにおける持続的発展と原子力エネルギー」
-COP は原子力の役割を認識すべきである-
2001年に最初にインドネシアから提案されたこのプロジェクトは、その後 2 回の専門家会合で議論され、改訂されて第 3 回本会合に提案された。そこで重要性は一致して認められたが、さらにコメントに基づいての計画の再検討が求められた。
今回の会合に一部修正した計画が討議され、 IAEA の専門家ログナー課長、アジア・太平洋エネルギー研究センター( APERC )のジュン副所長の講演等も参考にし、修正計画は実施に移すよう承認された。この計画で重要な点は、①各国が統一された計算コードを利用して、エネルギーの需給計画を作成し、供給計画におけるベストエネルギーミックス(原子力を含む)を提案し、排出される GHG を推定する。②その結果を統合し、この地域の全体のエネルギー需給と GHG 発生量の姿を把握する。③共同作業・検討会合には原子力関係者だけでなく、各国の「エネルギー」及び「地球環境」の関係者が参加する、などの点である。プロジェクト資金の見とおしが得られ次第、計画具体化のための国際会合を行う。 IAEA との連携も重要であるとログナー課長が指摘した。
4. 人材養成戦略
インドネシアの AINST ( Asian Institute of Nuclear Science and Technology )提案はその後のFNCAの人材養成ワークショップでの「アジアネットワーク大学」の討論、韓国政府による
IAEA への「国際原子力大学」の提案などを踏まえて、 2002 年 SOM でインドネシアが取り下げた。 2002 年 FNCA 本会合では韓国から
”Asian Networking of Higher Education and Training in Nuclear Technology(ANHETNT)
の提案があり、日本からはまず、人材のデータベースを整備しそれに基づく検討が必要であることが指摘された。これらを踏まえ、フィリッピン、オーストラリアからハイレベルの検討会合が提案された経緯がある。今回の会合では(1)人材データベース調査に基づき
FNCA として ANHETNT を検討する(2) IAEA が韓国との協力でアジア原子力教育・訓練ネットワークを検討中(3)フィリッピンは大学学部卒業後に
FNCA 参加国で修士、博士を取得させたいとの希望(4)マレーシアからは現在の「研究交流制度」の滞在期間を2-3年に延長することで、修士、博士の学位の取得を可能にすることが効果的であるとの提案等が明らかになった。これらを考慮して今後さらに検討を行う。
5. 各国代表報告のハイライト
| (1) |
中国 で 2002年1年間に原発4基が運開。放射線利用の生産高は年間の150 億元(2160億円)達した。 |
| (2) |
インドネシア は 2016年頃に原発1号機の運転開始を期待。発電用エネルギー源の調査・分析を IAEA と協力で完了した。 |
| (3) |
韓国 は 2015 年までに原発 28 基の運転を目指す。 80%の国民が原発を支持している。「先端放射線利用研究センター」が 2005 年に活動開始、政府は原子力研究開発予算の30%は放射線利用に充当されることとしている。 10MeV×100kw の電子加速器 2003年完成予定。テグ市染色工場団地廃水電子線による浄化実用装置の建設( IAEA と韓国政府の支援)の検討を開始した。 |
| (4) |
マレーシア は PET の1号機は 2004年中葉に運開、ガンマーグリーンハウスは2003年建設の予定である。電子線利用研究は高分子改質、排煙処理、表面塗装などである。 |
| (5) |
フィリッピン の原子力研究所 PNRI は安全規制担当副所長のポスト新設し、規制強化を図る計画である。電子加速器設置について JICA プロジェクト申請を提案中。 |
| (6) |
ベトナム では 2002年3月に設置された国家原子力発電開発運営委員会が 12月に原発のプレFSの結論を報告する予定。原発に向けて最大の問題は質的・量的に原子力人材が不足していることである。 |
| (7) |
タイ は新機構の OAP (タイ原子力庁)と TINT (タイ原子力技術研究所)が動き出した。新研究炉の建設は遅れているが、完成が待たれている。 |
むすび
原子力は現在・未来の社会に役立つ多くの可能性をもっている。「農業」、「医療」、「環境」、「安全」などの分野を中心に FNCA の国の研究者、政策担当者がこの国際協力を実際的効果のあるものにしようと熱意をもって取組んでおり、その成果が除々に表れている。我国の貢献は FNCA 活動のリーダー及びスポンサーとして各国から高く評価されている。多国間技術協力の良いモデルとなりつつあり、 IAEA もその結果に強い関心をもっている。
|