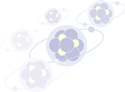|
第19回コーディネーター会合
2018年3月22日
東京 三田共用会議所
2018年3月22日(木)、内閣府・原子力委員会の主催、文部科学省による共催の下、第19回FNCAコーディネーター会合が東京において開催されました。FNCA日本コーディネーターである和田智明氏が会合議長を務めました。
会合には、FNCA参加11ヵ国(オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナム)の他、RCA地域オフィスから代表が出席しました。(韓国は都合により欠席)
結果概要は以下の通りです。
セッション 1:開会セッション
和田FNCA日本コーディネーターの開会宣言に続き、岡芳明原子力委員会委員長及び進藤秀夫内閣府大臣官房審議官が歓迎挨拶を行いました。岡原子力委員会委員長は、2017年度に策定された「原子力利用の基本的考え方」に触れて日本の取り組みを紹介するとともに、本会合の成功とFNCA活動のさらなる発展を祈願しました。進藤内閣府大臣官房審議官は、FNCAの沿革を紹介するとともに、関連活動として国際原子力エネルギー協力フレームワーク(IFNEC)、ならびにIAEA原子力科学技術閣僚会議に触れ、これらの場を活用しFNCA活動の周知に努めたいと述べました。
続いて参加者が自己紹介を行い、会合プログラムが修正なく承認されました。

|

|
 |
(左上)岡原子力委員会委員長
(右上)和田FNCA日本コーディネーター
(下)進藤内閣府大臣官房審議官
|
セッション2:第18回大臣級会合の概要
カザフスタン国立原子力センター科学官のウラジーミル・ビチュク氏より、2017年10月にカザフスタンアスタナ市において開催された第18回大臣級会合(MLM)の概要が紹介されました。会合では、「環境保全への原子力科学技術の応用」をテーマとして政策討論を行い、今後促進すべきテーマ・活動、及び参加各国の環境保全に関する取り組みへの支援・協力等に言及した共同コミュニケが採択されたことが報告されました。
セッション3:放射線利用開発分野におけるプロジェクト活動成果報告
- 放射線育種
本プロジェクトでは、持続可能な農業の促進を目指し、アジア各国でニーズの高い作物を対象に、放射線照射による突然変異育種技術を利用することで、気候変動下においても多収で様々な環境耐性を持つ新品種の開発を目指しています。今次会合では、「持続可能な農業のためのイネの突然変異育種」の活動について、ほとんど全ての参加国において各国のニーズに合った突然変異品種が作出され、うち数品種が実用化され大きな経済効果をもたらしており、成功裡に終了したことが報告されました。また、2018年度からは「気候変動下における低投入の持続可能型農業に向けた主要作物の突然変異育種」をテーマとして新たな活動を開始することが提案されました。
- バイオ肥料
本プロジェクトでは、放射線滅菌技術を製造過程に取り入れることにより、より高品質なバイオ肥料や、植物の生長促進効果とともに病害抑制効果を持つ多機能なバイオ肥料を開発し、環境に優しい農業の推進を図っています。今次会合では、3年間の活動成果として、各国における様々なタイプの多機能バイオ肥料開発とエンドユーザーへの普及、FNCAバイオ肥料ガイドライン第2冊「放射線技術を利用したバイオ肥料キャリアの生産」の発行、バイオ肥料開発による環境負荷の軽減と持続可能な農業への貢献等が紹介されました。また、2018年度からは電子加速器利用プロジェクトと合流し新プロジェクトとしてスタートすることが提案されました。
- 電子加速器利用
本プロジェクトでは、天然高分子に分解、橋かけ、グラフト重合等の放射線加工技術を施し、オリゴキトサン植物生長促進剤や土壌改良材としての超吸水材を作成し、フィールド試験を実施しています。今次会合では、3年間の活動の成果として、環境に優しい製品である植物生長促進剤と超吸水材により、多様な作物の収量が上がり、参加国に経済的な利益をもたらしたこと等が報告されました。また、2018年度からはバイオ肥料プロジェクトと合流し「放射線加工および高分子改質(仮)」をテーマとして新たな活動を開始することが提案されました。
- 気候変動科学
本プロジェクトでは、原子力技術及び同位体を用いた分析を通じ、過去の気候変動の仕組みと過程を理解し、新たな知見を解明するための専門知識共有を目的として2017年に活動を開始しました。今次会合では、本プロジェクトの概要、第1回ワークショップの開催結果、ならびに課題が紹介され、今後のテーマとして「環境アーカイブ」と「炭素貯蔵」をテーマとして取り上げていくことが報告されました。また、関連する分野として海産物生産地プロジェクトが提案されました。
- 放射線治療
本プロジェクトでは、アジア地域で発生頻度の高いがんに対する最適な治療法の確立と治療成績の向上、またアジア地域における放射線治療の普及を目指して活動を行っています。今次会合では、子宮頸がん、上咽頭がん、乳がんに関する長年の治験により良好な治療成績が得られており、FNCAの治療手順が参加国における標準治療手順になりつつあることが報告されました。また、最先端技術を用いた新たな子宮頸がん治療、参加国における品質管理/品質保証調査による放射線治療の品質向上、人材育成、ならびにアジアにおける国際協力強化等の取り組みが紹介されました。
セッション4:研究炉利用開発分野におけるプロジェクト活動成果報告
- 研究炉利用
本プロジェクトでは、多様な目的で利用される研究用原子炉について、アジア諸国の研究者間での相互協力を図っています。また、日本の研究炉における経験を基に各国の研究炉に関わる研究者の人材育成に寄与することを目指して活動を行っています。中性子放射化分析グループでは、「大気汚染」及び「鉱物資源」をテーマとして順調に活動が進められており、エンドユーザーとの連携維持・強化に取り組んでいることが報告されました。また、研究炉利用グループでは、「医療/産業用アイソトープ製造」と「新規研究炉」の2課題について情報交換と議論を行い、今後、ホウ素中性子捕捉療法や材料研究等の議題を取り上げることが報告されました。
セッション5:原子力安全強化分野におけるプロジェクト活動成果報告
- 放射性廃棄物管理
本プロジェクトでは、原子力/放射線関連施設における放射線安全の確保について知見を共有し、各国の安全レベルの向上を図るとともに、一般公衆の放射線安全確保のために放射性廃棄物の処理・処分方法や環境影響評価について情報共有を行っています。今次会合では、低レベル放射性廃棄物処分場、及び放射性廃棄物と使用済燃料管理に関する各国の現状について情報共有を行い、3年間の活動計画の一つとして「低レベル放射性廃棄物処分場に関する統合化報告書」の作成を進めていること等が報告されました。
セッション6:原子力基盤強化分野におけるプロジェクト活動成果報告
- 核セキュリティ・保障措置
本プロジェクトでは、原子力平和利用の推進において必要となる原子力安全及び核セキュリティ・保障措置の一層の確保について、知識・情報の共有、ならびに人材育成協力の推進等による強化を図っています。今次会合では、1)核セキュリティ(核鑑識、核セキュリティ文化、放射線源のセキュリティ)、2)保障措置(追加議定書実施)、ならびに3)核セキュリティ・保障措置分野の人材育成をテーマとして多様な議論が進められていること等が紹介されました。
セッション7:RCAとFNCA間の協力に関するRCAからの活動報告
RCAは、アジア・太平洋地域の加盟国を対象とした原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定に基づき、加盟国間の技術支援協力を行うIAEAの事業であり、FNCA参加国より11ヵ国及び非FNCA参加国11ヵ国(インド、パキスタン、スリランカ等)の22ヵ国が参加しています。今次会合では、イム・ジンギュRCA地域事務所総務課長が出席し、RCAプロジェクト及び地域事務所の活動概要が紹介された。RCAとFNCAの今後の協力について、放射線育種、放射線治療、電子加速器利用の各分野において、情報共有及び会合の相互参加を中心に協力を続けていくこと、また、一層の協力強化に向けて、FNCAとRCAの活動促進と相互理解を図っていくことが確認されました。

|
|
会合の様子
|
セッション8:新規プロジェクトに関する提案
タイより、新規プロジェクト「原子力発電所及び研究炉のためのリスクコミュニケーション戦略に関する研究開発プロジェクト」について、詳細な提案内容が説明されました。
また、新規提案プロジェクトに関する予算確保ついて、評価の枠組みに詳細が記載されていないとの指摘がありました。これに対し事務局より、当該枠組みは昨年度に運用を開始し、今後運用していく中で課題の改善を図っていくことが必要であり、本議題は次回の上級行政官会合(SOM)において議論できるよう準備を進めたいと述べられました。
セッション9:FNCA活動の今後の活動について
和田FNCA日本コーディネーターより、3件の新規プロジェクト提案について総括評価が提示され、各提案について各国からの講評と議論が行われました。この結果、2件の新規プロジェクト(「放射線育種プロジェクト」及び「加速器利用プロジェクト(農業、環境、医療応用のための放射線加工と高分子改質)」(「電子加速器利用プロジェクト」と「バイオ肥料プロジェクト」を統合))が承認されました。「原子力発電所及び研究炉のためのリスクコミュニケーション戦略に関する研究開発プロジェクト」については、数か国からの評価スコアが低かったため採決とならなかったものの、第17回MLMの新たなに方向性に沿うものであり、次回コーディネーター会合において再提案されることが推奨されました。続いて評価年を迎えたプロジェクト成果の評価が発表され確認されました。最後に、2018年度の活動計画が提示され承認されました。
セッション10:閉会
和田FNCA日本コーディネーターより今次会合の「結論と提言」案が提示され、討議の結果合意されました。
結論と提言(仮訳)
| 1. |
会合は、2017年度に於けるFNCAの活動が効果的に行われ、参加各国にとって有益な結果がもたらされた事を評価する。
|
| 2. |
会合は、2017年の第18回MLMコミュニケで採択された、FNCAの取るべき新しい方向性に沿って、放射線育種、加速器利用(農業、環境、医療応用のための放射線加工と高分子改質)、放射線治療、気候変動科学、そして更に原子力安全と安全保障分野に於ける、いずれも参加国の持続可能な発展に寄与するプロジェクトを促進することで、原子力科学と技術の応用に関するFNCAの活動を更に進めることに合意する。 |
| 3. |
会合は、2018年3月をもって活動を終了する3プロジェクト、即ち、a)放射線育種、b)バイオ肥料、c)電子加速器利用について、終了評価を実施した。夫々の評価結果とコメントは以下の通りである。
|
| |
a) |
放射線育種 |
|
|
- 旱魃、高温、低温、洪水、塩害、気温の大きな変化、病虫害といった様々な環境ストレスに耐性を有するイネの複数の突然変異種の作出に成功した
- 内、幾つかの突然変異種は農業従事者に提供されるべく、公式登録をしており、参加国に大きな経済的貢献をもたらす
- このプロジェクトを通じて得られた試験データは、近い将来、低投入/高収穫に適した突然変異種作出の可能性を示唆している
|
| |
b) |
バイオ肥料 |
| |
|
- 様々な種類の多機能バイオ肥料が開発され、参加国の多くでエンドユーザーに提供されている
- FNCAバイオ肥料ガイドライン第2冊「放射線技術を利用したバイオ肥料キャリアの生産」が今年3月に出版されている
|
| |
c) |
電子加速器利用 |
| |
|
- このプロジェクトは、穀物収穫高を上げるために、放射線加工技術を利用した高機能植物生長促進剤(PGP)と超吸水材(SWA)の開発が目的であった
- 参加国の多くで、PGPの開発による一般穀物の高収穫化に成功し、すでに実用化されている国もある
- 「放射線加工によるハイドロゲル及びオリゴ糖類の開発に関するFNCAガイドライン」は2017年に更新された
|
| 4. |
第17回MLMで更新合意されたプロジェクト評価プロセスに沿って、3プロジェクトの妥当性、有効性、効果、及び継続性について、全参加国による事前評価が実施された。その結果、期間3年の加速器利用プロジェクト(農業、環境、医療応用のための放射線加工と高分子改質プロジェクト)(従来の電子加速器利用とバイオ肥料プロジェクトの融合)、及び期間5年の新規フェーズの放射線育種プロジェクトが新しくスタートすることとなった。夫々のプロジェクトに関するリマークは以下の通りである。
|
| |
a) |
放射線育種 |
| |
|
- 本プロジェクトは、食料安全保障と気候変動インパクトの軽減を含んだ、農業分野での効果が期待される
- プロジェクトの効果は社会経済に大きな影響を与えると予測される他、原子力科学・技術応用の好例となり得る
- 日本からのイオンビーム照射技術と他メンバー国との協力は結果創出の効率上昇を生む
- 会議やフィールドトリップを通じたプロジェクト結果の普及は有用である
|
| |
a) |
加速器利用(農業、環境、医療応用のための放射線加工と高分子改質) |
| |
|
- 本プロジェクトは強靱なインフラの整備、包括的で持続可能な産業化の推進及びイ技術革新の拡大を図る持続可能な開発目標(SDGs)の一端を志向するものである
- メンバー国間の協力をもって、プロジェクトは生活の質的向上、環境保護及び経済的発展に寄与するものと期待される
- 研究結果の実務的運用にとって、公的機関による技術移転政策とインフラ開発支援は極めて重要である
- 放射線によるナノ物質やナノ複合材料の合成とその応用については、将来的にこのプロジェクトに於いて検討する
- 本プロジェクトは、加速器を使った研究対象が広範囲に亘る為、各参加国から最低二名の専門科学者の参加を要する(内、1名がプロジェクトリーダーとなる)
|
|
5.
|
「原子力発電炉または研究炉設置に際するリスクコミュニケーション戦略についての研究プロジェクト」の提案に関しては、4つの評価範疇について、複数の参加国が「Low」スコア評価をする結果となった。しかしながら、この新規提案は2016年のMLM採択のFNCA方針に沿ったものであり、別の評価範疇では高スコアの評価を得ていることから、次回CDMでの再提案を推奨する。 |
|
6.
|
新規プロジェクトを立ち上げる際に重要な、具体的な予算措置の規定が不備であることが指摘されており、次のSOMで議論される事とする。 |
|
7.
|
現在継続中の5プロジェクト、気候変動科学、放射線治療、研究炉利用、放射線安全・廃棄物管理、および核セキュリティ・保障措置は「放射線利用開発」「研究炉利用」「原子力安全強化」「原子力基盤強化」の夫々の分野に於いて、参加国間の協力の下、有効に実施されていることを確認した。夫々のプロジェクトに対するコメントは以下の通りである。 |
| |
a) |
子宮頸がんの治療プロトコル(CERVIX-V)に用いられる3D-IGBTは最先端技術である為、2018年度ワークショップに於いては治療従事者に対する3D-IGBTの実務的研修コースを設けることを推奨したい |
| |
b) |
加速器質量分析(AMS)による同位体・核種分析は、現在オーストラリアと日本でのみ可能である為、気候変動科学プロジェクトに於いて、参加各国に対する技術移転と人材開発を実現することを目的に加えることを推奨する |
| |
c) |
研究炉利用プロジェクトの中性子放射化分析(NAA)リーダーは、現行のPM2.5と希土類元素のプログラム終了までに、潜在的エンドユーザーとの関係構築について積極的に行動することを推奨する |
| |
d) |
核鑑識能力は、各国の核セキュリティ体制維持の為の核心と認識されるため、核セキュリティ・保障措置プロジェクトに於いての核鑑識分析と人材開発の協力を通じて、参加各国が核鑑識能力の拡充に努力することを推奨する |
| |
e) |
放射線安全・廃棄物管理プロジェクト参加国間の現況と要求が多岐に亘ることに鑑み、低レベル放射性廃棄物処分場の総論、及び各国の現状を含んだレポートをまとめるという方針に賛同する |
|
8.
|
水産物由来調査プロジェクトが、今回、オーストラリアから新規プロジェクト候補として紹介された。 |
|
9.
|
FNCAは継続してIAEA/RCAと、放射線育種、放射線治療、及び加速器利用(農業、環境、医療応用のための放射線加工と高分子改質)の各プロジェクトについて、その相乗効果と非FNCA国との経験共有の為に、協力関係を維持する。 |
|
10.
|
2018年度の各プロジェクトワークショップはAnnexに示された主催国で夫々行われることになるので、各ホスト国は、主催の確認をできるだけ早くお願いする。 |
|
11.
|
本CDMのサマリーレポート(案)が2週間以内にメール配信されるので、各CDは、受領後2週間以内にコメントを返す様、お願いする。事務局で最終版を調整する。 |
|