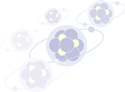|
第7回 コーディネーター会合
2006年3月1日〜3日、東京 KFCビル
第7回FNCAコーディネーター会合(CM:Coordinators Meeting)が2006年3月1日から3日まで、原子力委員会と内閣府の主催により都内で開催された。この会合には、9カ国のコーディネーターや代表者、専門家、政府関係者が参加した。またオブザーバー参加としてバングラデシュと IAEA が本会合に参加した。
主な出席者は以下の通りである。 豪州 :キャメロン豪州原子力科学技術機構専務理事
中国 :ジャンチン中国国家原子能機構国際合作司司長
インドネシア :スントノ原子力庁長官
日本 :町 原子力委員会委員
韓国 :パク科学技術省原子力協力局次長
マレーシア :アドナン原子力庁次官
フィリピン :ベルニド原子力研究所副所長
タイ :マヌーン原子力庁長官
ベトナム :原子力委員会副委員長
オブザーバー参加
バングラデシュ:アジズ原子力委員会委員 バイオ科学担当
IAEA :ナルールIAEA/RCA議長 マレーシア原子力庁副長官
 |
| 各国参加者 |
1.プロジェクトの活動
現在、実施中の 8分野12プロジェクトの内、以下の3分野3プロジェクトが評価の対象となった。
□ 農業利用
1)バイオ肥料
根粒菌や菌根菌などの微生物を利用して作物生産を高める目的のバイオ肥料プロジェクトについては、 2003年から2005年に各国で実施された圃場実証により、さまざまな作物の収量が2〜122%も増加した結果が得られた。また、各国で実施された経済分析では、バイオ肥料の利用により化学肥料の利用を20〜50%減らせる可能性があることが示された。フィリピンのケースでは農業従事者の純所得が58%も増加するという結果が得られた。本プロジェクトの評価が行われ、 熱滅菌の担体を使用したバイオ肥料と、放射線照射滅菌の担体を使用したバイオ肥料の QA/QC 比較、担体滅菌に最適な放射線処理方法の定義、バイオ肥料利用の拡大に向けた戦略計画の策定(圃場試験を含む)を行うため、プロジェクトを1年間延長することが合意された。
□原子力安全文化
オーストラリアより、ベトナム(2002年)、韓国(2003年)、およびインドネシア(2005年)で実施された研究炉の関する安全文化ピアレビューに進展が見られる状況が発表され、次回のピアレビューはマレーシアで開催されることが確認された。本プロジェクトの評価が行われ、プロジェクトが社会・経済に影響を与え、すべての参加国で大きな成果が得られたことで、期間を3年間延長し、自己評価、ピアレビュー、および他の活動との統合を活動内容に組み込み、研究炉の安全性に関する行動規範の影響を考察することが合意された。
□工業利用:電子加速器
低エネルギー EB 加速器の液体天然高分子への応用(日本)、薄膜(マレーシア)、排煙処理(中国)、および廃水処理(韓国)に関するワークショップと実演の成功や、参加諸国におけるプロジェクトの主な成果が報告された。本プロジェクトの評価が行われ、第2段階(2006〜2008年)として、天然高分子の放射線分解と橋かけ、および排水の放射線処理に重点を置いて取り組むというが提案が示された。日本コーディネーターが、大きな成果が得られたことを指摘し、本プロジェクトを2年間に限って延長することを提案した。さらにプロジェクトの工業・商業応用に関する目標を達成するには、エンドユーザーとの連携を図ることが重要であるとコメントした。
残り6分野9プロジェクトについては以下の報告がなされた。
□人材養成と ANTEP
原子力の平和利用の進展には、これに携わる人材の養成が不可欠。原子力発電を導入しようとする国だけでなく、放射線利用を普及・発展させようとする国にとっても、人材の確保が最優先である。
2005年12月に東京で開催された第6回FNCA大臣級会合において、FNCA参加9カ国の科学技術担当大臣は、「アジアにおける人材養成」のトピックスについての討議を行った。この討議の中で、各国が持っている人材養成のニーズとプログラムを有機的に連携させるネットワークである「アジア原子力教育訓練プログラム(ANTEP)」構想について合意された。この合意のもと、各国の人材養成プロジェクト・リーダー(PL)が中心となって、自国における人材養成の必要な分野(ニーズ)と他国に対して提供できる貢献内容(プログラム)について把握するためのアンケート調査を実施した。本会合で、この結果が各国に提示され、今後の具体的な進め方やスケジュールなどについて討議され、主に以下の点について一定の合意を得た。
| ・ |
各国代表は、 ANTEPの重要性を認識 |
| ・ |
人材養成ニーズと貢献プログラムについて議論され、さらに詳細事項についてアンケート調査を早急に実施すること |
| ・ |
各国コーディネーターが人材養成ニーズと貢献可能なプログラムについての協議を可能な限り早く実施すること |
| ・ |
2006年夏に中国で開催される人材養成WSにおいて、進捗状況およびANTEP活動について討議し、その結果を次回の大臣級会合に報告すること |

□農業利用
1) 放射線育種
干ばつや病気に強い新しい品種の開発を目指している本プロジェクトについては、乾燥に強いソルガムおよびダイズの突然変異育種が順調に開発され着実に成果が出ていることが報告された。耐虫性ランおよび耐病性バナナに関する品種開発についても引き続き研究が進められていること、2007年から実施予定の新しいサブプロジェクトに関しては、イネ、ダイズ、小麦、およびソルガムに対象を絞って成分改変または品質改良育種を目的に取り組むことが合意された。
□研究炉利用
1) 中性子放射化分析
健康被害をもたらず環境汚染の一つである空気中浮遊塵の分析(中性子放射化分析)のプロジェクトについては、各国が自国の 環境管理当局と緊密に連携し、環境政策にモニタリングの結果を反映させることの重要性が指摘された。
2)研究炉基盤技術
研究炉の炉心管理のための中性子計算技術を参加各国で共有することを目指す研究炉基盤技術プロジェクトについては、各国は日本が提供した中性子計算コードの SRAC を用いた炉心計算に成功し、良好な結果を得ることができた。本プロジェクトにより、ラジオアイソトープ製造などの研究炉の高度な活用だけでなく、安定かつ安全な運転にも資することが指摘され各国代表から支持が得られた。
3)Tc-99m ジェネレーター
本プロジェクトで PZC 型 Tc-99m ジェネレーター製造の新技術が確立されたこと、事業計画に関する提案など、各国での定常生産に向けた計画が報告された。品質保証と PZC 素材、Tc-99m および Tc-99m で標識された臨床用途向け化合物についての討議が行われたが、さらに PZC 技術の普及を進めるため、標準マニュアルを作成し、刊行することが示された。
□医学利用
1)放射線治療
子宮頚がんの治療について、新 しい治療手順が共同臨床研究により試験され、それに基づく 5 年生存率 が、それぞれ 53% と 66% と高い治療実績を示したことが報告された。放射線治療の QA/QC は実施されており、参加 7か国(インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)の結果は許容範囲内であったことが報告された。
2)医療用 PET・サイクロトロン
マレーシアのプロジェクトリーダーから、新規プロジェクトの計画が発表された。 FNCA 参加国がプロジェクトに参加するため、プロジェクトリーダーがすでに指名されており、第 1 回プロジェクトリーダー会合( PLM )は 2006 年にマレーシアで開催。同会合では、計測機器、医薬品、および診断に関する実行計画について討議されることなどについて各国間で合意された。
□放射性廃棄物
本プロジェクトでインドネシアとフィリピンで実施した、原子力施設の廃止措置とクリアランスに関するタスクグループ活動について報告された。また、放射性廃棄物管理統合報告書を 2006 年に改訂する予定であることが報告された。日本コーディネーターは、使用済放射線源、TENORM 、および NORM の管理などについて、さまざまな専門家によるミッションやタスクグループから提示された勧告を実施し、プロジェクトを確実に成功させるには、参加国によるフォローアップ活動が重要になると強調した。
□原子力広報
一般国民だけでなく専門家集団との双方向のコミュニケーション、メディアなどとの効果的なコミュニケーション手段の開発および利用、地域スピーカーズ・ビュローの利用、および原子力コミュニケーターの養成 の必要性が報告された。原子力エネルギーのさまざまな側面に関し、一般国民を啓蒙し、正確な情報を提供して、原子力エネルギーがより広く受け入れられるようにするには、PI が重要となることが各国で認識さ れた。
| 2. 「第6回FNCA大臣級会合」報告 |
| |
|
|
|
| |
|
|
日本コーディネーターより、2005年12月に東京で開催された第6回大臣級会合の概要が報告された。科学技術と原子力のテーマで松田大臣がリードオフ・スピーチを行い、原子力は基礎物理、生物学、新材料開発、IT技術、医学等の広い分野の科学技術の発展に大きな役割を果たす事が指摘されたこと、人材養成ANTEPがすべての代表者により支持されたことを強調した。 |
| |
町日本コーディネーター報告 |
3.「アジアの持続的発展における原子力エネルギーの役割」パネル
日本コーディネーターより、2006年1月に東京で開催された第2回パネル会合の結果が報告された。各国代表からは、廃棄物の管理および処理、燃料の供給やリサイクルを含むエネルギー供給の安定性と持続可能性、原子力のCDMへの組み込みなどの問題が指摘された。
|
4. 特別講演 |
| |
|
|
|
IAEA/RCA議長Dr. Nahrul Khair Alang Md. Rashidが、現在のIAEA/RCAの活動状況と達成状況について講演を行った。 RCA と FNCA では構造やアプローチが異なるが、共通の目標もあること、また、資源を効果的に利用するため、 2 つの地域プログラムを収束することが提案された。
また、各国代表は、RCA と FNCA が情報と資源を共有する機会を引き続き模索するべきであるという見解を共有した。
|
|
|
|
○ バングラデシュ原子力委員会( BAEC )バイオ科学担当委員の Dr. Abdul Aziz が、「原子力科学技術プログラムおよび活動の概要」と「バイオ肥料」について講演を行った。
バングラデシュの包括的な原子力プログラムに関して、発電所の運転と保守、アイソトープ製造、医療サービスと研究、保健物理学と放射線監視、非破壊試験、提案中のルプールにおける原子力発電プロジェクトなどが含まれた。 |
|
|
|
| |
 |
レセプション挨拶 近藤原子力委員長 |
|
バイオ肥料シナリオについて、窒素を固定するシアノバクテリアを持つ水生シダのアカウキクサの効果的利用を強調すると同時に、コメなどの多くの作物での幅広い利用に向けて、アカウキクサの効果的な栽培についても言及した。また、放射線技術を利用し、耐虫性を高めた新種のアカウキクサを開発するべきであると強調した。 |
|
|