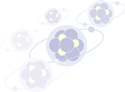|
第9回 コーディネーター会合
2008年3月10〜11日、東京 三田共用会議所
 2008年3月10日(月)から11日(火)まで、内閣府原子力委員会主催、文部科学省後援による第9回FNCAコーディネーター会合が東京(三田共用会議所)において開催された。オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの10ヵ国のコーディネーターが参加するとともに、IAEAがオブザーバーとして参加した。我が国からは、近藤原子力委員会委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員及び関係省庁(内閣府、文科省、外務省、経産省)の行政官並びに町FNCA日本コーディネーター等が参加した。 2008年3月10日(月)から11日(火)まで、内閣府原子力委員会主催、文部科学省後援による第9回FNCAコーディネーター会合が東京(三田共用会議所)において開催された。オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの10ヵ国のコーディネーターが参加するとともに、IAEAがオブザーバーとして参加した。我が国からは、近藤原子力委員会委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員及び関係省庁(内閣府、文科省、外務省、経産省)の行政官並びに町FNCA日本コーディネーター等が参加した。
今次会合では、次の主要議題について議論が行われた。
【主要議題】
 |
原子力の平和利用に関する8分野11プロジェクトの活動報告、評価及び今後の計画 |
 |
第8回FNCA大臣級会合の報告及び「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するアジア原子力協力フォーラム(FNCA)共同コミュニケ」のフォローアップ |
 |
「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」の報告及び今後の計画 |
 |
FNCAとIAEA/RCA との協力活動について |
 |
FNCAの今後の課題について |
セッション毎の会合概要は次の通り。
1. セッション1:プロジェクトの評価
下記の8分野11プロジェクトについて、活動報告、評価及び今後の計画について議論が行われた。
 |
研究炉利用分野 |
| |
- 研究炉基盤技術プロジェクト※ |
| |
- 中性子放射化分析プロジェクト※ |
 |
医学利用分野 |
| |
- 医療用PET・サイクロトロンプロジェクト |
| |
- 放射線治療プロジェクト※ |
 |
農業利用分野 |
| |
- 放射線育種プロジェクト |
| |
- バイオ肥料プロジェクト |
 |
工業利用分野:天然高分子の放射線処理プロジェクト |
 |
原子力広報プロジェクト※ |
 |
人材養成プロジェクト※ |
 |
原子力安全文化プロジェクト |
 |
放射性廃棄物管理プロジェクト※ |
なお、研究炉基盤技術・中性子放射化分析・放射線治療・原子力広報・人材養成・放射性廃棄物管理の計6プロジェクトは、今年度で3ヵ年の計画が完了するため、今次会合で評価を受けたプロジェクトである(※が評価対象プロジェクト)。
1) 研究炉利用分野
 |
研究炉基盤技術プロジェクト※ |
- 本プロジェクトは、研究炉の安全かつ安定的な運転がさらに進み、効率的に研究炉を利用する基盤を強化するため、炉心管理に関する核計算技術の向上を目指しており、プロジェクトの中で共有している中性炉解析用標準コード(SRAC)又は連続エネルギーモンテカルロコード(MVP)を、RI 製造や宝石用原石の照射などに用いる研究炉の解析に利用している。
- 会合では、次期プロジェクトのテーマ「研究炉の安全運転のための安全解析技術」とすることに合意するとともに、計算コードとしてJAEA が開発した安全解析コードである「COOLOD」及び「EUREKA」を適用し、3年間(2008-2011年)プロジェクトを延長することが了承された。また、従来のSRACやMVP コードについても引き続きフォローを行うことが確認された。
|
 |
中性子放射化分析プロジェクト※ |
- 中性子放射化分析(NAA)は、分析対象物(試科)に中性子照射して構成元素を放射化させ、その放射能およびエネルギーを測定して元素分析を行う手法であり、試料の化学組成を高感度で分析することが可能である。第2期プロジェクト(2004-2007年)では環境試料を分析対象として大気中浮遊塵などの環境汚染モニタリングを進めてきた。
- 第3期プロジェクト(2008-2010年)では、環境試料に加え、地球化学試料及び食料試料を分析対象とすることが合意された。また、他の分析手法とNAAの比較検討を行うことが要請され、合意された。
|
 |
テクネシウム99mジェネレータプロジェクト(2006年度終了)のフォロー |
- テクネシウム99mは核医学診断で最も多く利用されているラジオアイソトープであり、研究炉を利用して自給することにより安定供給の確保と外貨節約に貢献するものである。本プロジェクトは、製造技術の確立、生産方式の標準化、市場調査などを行い2007年3月に終了した。ベトナムとインドネシアで商業化が計画されており、会合では引き続き商業化に向けたフォローを行うこととした。
|
2) 医学利用
 |
医療用PET・サイクロトロンプロジェクト※ |
- 本プロジェクトは、先進技術を用いたがんなどの病気の早期発見、早期治療によりアジアの人々の健康増進を目的とし、核医学診断技術の向上と普及を目指し、医療用PET(陽電子放射断層撮像装置)及びサイクロトロン(医薬品用放射性核種を製造する電子加速器) について技術向上のための活動を行っている。
- 今次会合ではプロジェクトの進捗状況が報告され、その中で、サイクロトロン施設においてPET 検査で用いる放射性薬剤を製造し、同施設を持たない病院に配給するシステムを導入することにより、PET の運用費用を削減できることなどが報告された。
|
 |
放射線治療プロジェクト※ |
- 本プロジェクトは、アジア地域で患者が多い子宮頚癌(しきゅうけいがん)や上喉頭癌(じょういんとうがん)を対象とし、各国共通の治療手順を決め、その治療効果を比較しながら、アジア地域の標準となる治療方法の確立を目指している。
- 今次会合では、子宮頚がんと上喉頭がんの新たな治療手順の確立など明確な成果が得られたことが確認され、放射線がん治療のプロジェクトを新たに3年間拡張するとともに、照射線量の品質保証/品質管理( QA/QC )活動を2 年間実施することが承認された。
|
3) 農業利用
 |
放射線育種プロジェクト |
- 本プロジェクトは、放射線照射による作物の品種改良によって耐病性、耐虫害性、耐旱(ばつ)性などのすぐれた品種を作り出し、アジア地域における食糧増産に貢献することを目的とし、「バナナの耐病性育種」及び「ランの耐虫性育種」をサブプロジェクトとして進めてきた。
- 今次会合では、今後、新たなサブプロジェクトとして「イネの品質改良育種」を主要な活動とするとともに、従来の「ランの耐虫性育種」は2009 年までマレーシアでフォローを行い、「バナナの耐病性育種」は2008 年に終了とすることが合意された。なお、「イネの品質改良育種」については、生産性の改善を対象とすべきとの提案がなされ、今後検討を行うこととした。
|
 |
バイオ肥料プロジェクト |
- 本プロジェクトは、バイオ肥料技術を改良し普及させることによりアジア地域における食糧生産を増加させるとともに、化学肥料の使用を減らし環境と土壌の保全を図り、持続可能な農業を促進させることを目指している。
- 今次会合では、進捗状況が報告され、接種の品質の観点からは蒸気滅菌より放射線滅菌が有利であることが述べられるとともに、化学肥料の使用を減らし環境を保護するものとしてバイオ肥料の重要性が指摘された。
|
4) 工業利用
 |
天然高分子の放射線処理プロジェクト |
- 本プロジェクトは、適用範囲が広く安全性に優れた低エネルギーの電子加速器による照射システムを開発し、電子加速器のより広範な利用を促進することを目的としたもので、2007 年からIAEA/RCA と連携してプロジェクトを進めている。
- 今次会合では、進捗状況及び今後の計画(2006-2008年)が報告された。会合では、RCAのプログラムで設置されたインドネシア原子力庁の大型照射施設を用いたキトサン(化粧品・繊維・人工皮膚などに応用される高分子)の放射線照射の実施試験を行いたいとの本プロジェクトのワークショップにおける要請に対して、インドネシア代表はそれを歓迎するとした。
|
5) 原子力広報プロジェクト※
- 原子力の平和利用は国民の理解の下に進めていくことが必要であるとの認識の下、本プロジェクトは、アジア各国との情報交換を行いつつ、各国の特徴を取り入れたより効果的な広報活動の確立を目指している。
- 会合では活動成果が報告され、3 年間のプロジェクトの延長が承認された。また地球温暖化の緩和やエネルギーセキュリティーの確保の観点から原子力発電への認識が変化していることから、参加国にて原子力発電についての世論調査を行うことが提案され受諾された。
|
6) 人材養成プロジェクト※
- 本プロジェクトはアジア地域の原子力科学技術分野の人材養成におけるニーズの把握、情報交換、地域内での協力のあり方の検討などを通じて、同地域内の人材養成の交流の促進と原子力技術基盤の強化に役立てることを目的とし、現在は、各国で必要とされる人材養成のニーズと提供可能なプログラムをネットワーク化するアジア原子力教育訓練プログラム(ANTEP)を推進している。
- 今次会合では、原子力発電の導入を計画している国における人材の必要性から原子力発電にかかわる人材養成を強化すべきとの提案がなされた。日本からは、核物理、炉物理、原子炉工学など原子力発電の基礎知識に係わる教育訓練をANTEP の下で提供できること、中国や韓国などからは原子力発電技術に関する学術及び訓練プログラムを提供するこが述べられた。
|
7) 原子力安全文化プロジェクト
- 本プロジェクトは、アジア地域の原子力技術の安全を維持するため、関係者の安全に対する意識や取組みの向上を目指し、各国の研究炉のピアレビュー(専門家による相互検討)や、原子力安全に関する情報の交換などを実施しており、本会合では、進捗状況や成果及び今後の活動計画について議論が行われた。
- 本プロジェクトを主導するオーストラリアから、今後のプロジェクトの方向性を3月に開かれるワークショップの結果を持って決定するとともに、本プロジェクトにかわり研究炉設備における知識管理についての新たなプロジェクトを実施することも選択枝であることが述べられた。
|
8) 放射性廃棄物管理プロジェクト※
- 本プロジェクトは、放射性廃棄物管理の安全の維持・向上を目的に、廃止予定の原子炉施設や自然由来の放射性物質に対する取組みの調査や、各国の実情に合わせた最適の管理方法を検討するもので、今次会合では、プロジェクトの成果が報告された。
- 今次会合では、本プロジェクトを終了し、新たに放射線安全にかかわるプロジェクトが提案され議論が行われた。IAEA/RCA でも放射線安全に係わる幅広い活動が行われており、また、参加国では廃棄物管理技術や施設の改善が重要であることなどが述べられた。
- 今次会合では、新たなプロジェクトは、放射線安全に関連して、廃棄物管理の活動を継続すべきであることが合意された。
|

2. セッション2:プロジェクト評価と2008年計画
| ・ |
今次会合では、評価対象である6プロジェクト(研究炉基盤技術、中性子放射化分析、放射線治療、放射性廃棄物管理、原子力広報及び人材養成)について、評価レポートを確認し、新たに3年間(2008年-2011年)のプロジェクトの延長が承認された。 |
| ・ |
放射性廃棄物管理プロジェクトのテーマについては、今次会合での参加国の意見を考慮し再検討行う。 |
| ・ |
放射線育種のサブプロジェクトである「バナナの耐病性育種」については2008年に終了し、「ランの耐虫性育種」は2009年に終了する。 |
 3. セッション3:第8回大臣級会合の報告と共同コミュニケのフォローアップ 3. セッション3:第8回大臣級会合の報告と共同コミュニケのフォローアップ
- 第8回FNCA 大臣級会合の報告及び同会合で発出された「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するアジア原子力協力フォーラム(FNCA)共同コミュニケ」のフォローアップが行われた。
- 今次会合では、各国コーディネーターを通して共同コミュニケのフォローに係わる情報を共有することに合意した。なお、オーストラリア代表から、共同コミュニケを支持する国を増やすことや原子力の専門家と環境の専門家の間で議論を促進することが提案された。
- また、第9 回大臣級会合において、二酸化炭素排出の削減やエネルギーの持続性の観点から民生原子力発電の導入に関する政策対話を、十分に時間をかけて行うことが合意されるとともに、参加国は共同コミュニケの取組みの進捗を同会合へ報告を行うことが期待されるとした。
 |
4. セッション4:
「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」の報告及び今後の計画
2) 第1回検討パネル会合の報告とフォローアップ
- 人材養成に関する第1 回検討パネル会合の報告が行われるとともに、同会合での提案についてのフォローアップとして、FNCA データベースの作成及びそのケジュールなどが提案された。
- 今次会合では、原子力発電分野の人材養成についてのFNCA データベースを設計・構築するための7つのアプローチが合意された。
|
2) 第2回検討パネル会合の計画
- 第2回検討パネルのテーマとして「原子力安全」が提案され、第2 回検討パネルにおいて参加者は検討パネルの結果の評価及び原子力に関する次のステップを議論すべきであると、及び、原子力に関する技術基盤と社会基盤に関する情報交換と経験の共有を図るために、事務局が「FNCA 原子力セミナー」を提案する考えである旨説明が行われた。
- 意見交換の結果、第2回の検討パネルでは「原子力安全」をテーマとすること及び同会合の中で原子力発電に係わる次の取組みについて議論を行うことが合意された。
 |
5. セッション5:IAEA/RCAとの協力
- IAEAとFNCA双方から、FNCAとRCAの協力の成果について報告が行われた。
- IAEAから、FNCAとの協力活動を継続するとともに、次回のRCA会合において協力活動を強化する提案を検討することが表明されるとともに、参加国はFNCAとIAEAにおける協力と情報交換の強化を図る取組みを評価した。
- 今次会合では、これまでのステップは非常に重要なものであり、協力をさらに推進することで合意された。
|
6. セッション6:FNCAの課題
| ・ |
FNCA のビジョン声明(2000年に承認)に従って、FNCAは、原子力技術の平和目的で安全な利用において積極的に地域連携を行うことによって社会経済開発を強化するための効果的な手段として認められるべきであることを確認し、第8 回大臣級会合で提示されたFNCAの5つの課題、すなわち
 |
地域及び各国の優先事項との連関 |
 |
エンドユーザーとの協力の強化 |
 |
持続的な財政支援の確保 |
 |
他の地域活動との協力と活動の重複の最小化 |
 |
原子力発電導入に係わる人材養成の支援の必要性 |
について議論が行われた。
|
| ・ |
今次会合では、5つの課題と将来の方向性について参加各国から報告が行われた。今後、参加国が新規プロジェクトの立案や既存プロジェクトの評価を行う際には、これらの課題を考慮することを合意した。また、FNCA プロジェクトの成果のエンドユーザーとの連携を強化すべきであることが合意された。 |
|