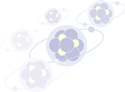|
第3回 コーディネーター会合要約
”実務レベルの協力 さらに深まる”
1.プロジェクト推進政策 -パートナーシップの一層の強化-
2000 年の大臣級会合において FNCA 枠組下での協力は原子力技術の特長を活かし、参加国のニーズに応えて、社会・経済的発展に効果のある成果を目指して、研究開発を進めるとの政策を明確にした。今回の会合ではこの政策に沿ってプロジェクトの計画及び実施が行われつつあることを確認した。
今後、プロジェクトの実施に際してパートナーシップを一層重視し、途上国のプロジェクト推進の責任を大幅に強化することで合意した。これによって途上国の研究・運営面の自立を促し、能力を高めることが出来る。もちろん、我が国は財政面を含めプロジェクト運営推進の責任を担い続ける。
2.「アジアの持続的発展」における原子力の重要性
-原子力エネルギーをCDM(クリーン開発メカニズム)に組み入れるために-
アジアはエネルギー資源の少ない地域である。一方、アジアは世界で最も大きい人口を抱えている。経済成長が大きく生活レベルが高くなりつつあるので、エネルギーの消費も急速に増えている。このような状況から、中国、韓国、インドネシア、ベトナム、日本はエネルギー資源の多様化と確保、地球温暖化防止の観点から原子力発電の導入あるいは増強が必要であるとの意見で一致した。また、新しいプロジェクトとして「持続的発展と原子力エネルギー」を開始することを次回大臣級 FNCA 会合に提案することになった。
このプロジェクトでは、 FNCA 各国が自国のエネルギーの需給戦略とその中での原子力エネルギーの位置付け、エネルギーミックスのあり方を検討し、意見交換を行う。それに基づき、地域全体のエネルギーの将来戦略を描く。一方、地球環境との関連では CDM に原子力を含ませるべきとの考えが、中国、韓国、日本、ベトナム、インドネシアの出席者から表明された。本件については、本プロジェクトの検討結果を踏まえ、各国のエネルギー政策及び原子力政策担当部局が京都議定書に責任を担当する部局と協議することにより政策を定めることになろう。また、京都議定書、 CDM 等につき情報交換の会議を FNCA が開催する事を希望するとタイ代表が提案した。
3.「放射線」に対する高校生の意識調査
―「原子力広報」プロジェクトで初の高校生の千人規模調査―
若い世代の原子力に対する正しい理解が重要であることから、生活につながりが深く、 FNCA 参加国の共通の利用分野である「放射線」について、各国約 1,100 人の高校生を対象に一斉調査を行うことが合意された。調査結果は今後の各国及び FNCA 広報活動に反映される。
4.「研究炉の安全文化ピアレビュー」の開始
研究炉は世界各国で老朽化が目立ち、安全の確保が重要な課題となっている。安全性の向上には、原子力に関係する全ての人々が安全の大切さを認識し、絶えず安全に心掛けること、経営の基本に安全を据えることなど、いわゆる「安全文化」が重要である。 FNCA の「原子力安全文化」プロジェクトはオーストラリアと日本の協力を中心に進めているが、今回初めて「研究炉の安全文化」の相互レビューが提案され、次回のワークショップが行われるベトナムで最初のピアレビューを 2 日間程度行うことが、ベトナムのボランティア提案で決定された。大きな進展である。
5.原子力人材養成戦略 ―原子力開発の基盤―
原子力を持続的に発展させるためには、人材の確保が不可欠であり、その戦略については、原子力計画に従って各国が策定する。一方 FNCA 参加国間の協力によって、各国の人材養成を支援することも求められている。
この点について、まず各国における「人材の不足度の現状」を分野毎に定量的に調査する。その結果は人材養成に関する今後の協力方策の立案に役立てることで合意された。
インドネシア提案の「アジア原子力科学技術大学」構想についてはマレーシア、日本等は FNCA 参加国に存在する原子力研究施設、大学を、それぞれの得意とする専門分野を生かして、「地域の研究・技術の拠点」として活用し、「アジア地域原子力教育・研究ネットワーク」を構築することが望ましいとの見解を表明した。今後、「人材養成」プロジェクトの中で検討を継続することで合意された。
6.新プロジェクト提案
ベトナムによる「原子力分析技術を活用しての海洋汚染の調査」及びインドネシアによる「原子力計測機器の保守、整備の地域ネットワークの設立」の2つのプロジェクトが提案された。前者については RCA 計画との連携などについて意見があり、今後,提案国と FNCA 日本コーディネーターによる検討を進め、第3回 FNCA 本会合に報告することで合意された。
7.効率的放射線「がん治療」 -アジアの女性をがんから救う-
アジアでは「子宮頚がん」が女性に一番多いがんである。 FNCA では放射線治療法における効率的照射手順を提案、各国の病院で臨床試験してⅢB期の患者の 5 年後生存率 54% を達成するという良い成績を上げた。今後この治療法をさらに高度化するとともに普及させる計画である。
8.食糧の確保に向けて -環境と共生する農業-
食料の確保は人口の多い途上国にとって重要な課題である。放射線による「品種改良」を利用し、東南アジアに多い乾燥地でも育つことができる耐旱魃性のソルガム(こうりゃん類の穀物で主食の一つ)と、大豆の開発を進めることが合意された。
また、化学窒素肥料の代わりに、微生物の作用を利用した「バイオ肥料」を製造、普及させるプロジェクトが開始された。この肥料は豆科や稲に効果があり収穫を 20 ~ 60 %も増加させることが出来る。化学肥料のような地下水の汚染が無く、コストも化学肥料の数分の一と安く、「環境にやさしい肥料」である。
FNCA プロジェクト推進に向けての課題
1.「アジアにおける持続的発展と原子力エネルギー」の進め方
各国から原子力政策の担当者のみならず、エネルギー政策及び地域環境対策の関係者の参加によって検討を進めて行くことが必要である。そのために各国の FNCA 上級行政官による調整が求められる。わが国においても経済産業省など関係省庁の参加が必要である。
2.各国における国家開発計画の中での FNCA 活動の位置付けの一層の明確化が必要である。
3.FNCA プロジェクトの推進に有用な研究者の交流を活発にすることが必要である。このための現行の文部科学省の原子力研究交流制度の活用を可能にすることが望まれる。
|