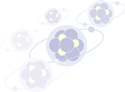ソウル(韓国)
2002年10月31日 |
|
 |
| 一堂に会したFNCA大臣級会合(MM)の参加者 |
|
| |
| 1. |
第3回アジア原子力協力フォーラム(FNCA)は韓国ソウル市で、2002年10月30日から31日にかけて「次世代のための原子力」を基調テーマに開催された。アジアの9カ国、すなわちオーストラリア、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、からの平和目的の原子力研究開発利用に責任をもつ大臣と上級行政官、また国際原子力機関(IAEA)ならびに地域機関からのオブザーバーも参加した。
第3回FNCA本会合の大臣級会合(MM)は韓国の蔡永福科学技術大臣の歓迎挨拶、引き続いての日本の細田博之科学技術政策担当大臣の祝辞、同じく日本の藤家洋一原子力委員長の開会挨拶により開会した。議長である韓国の李昌健原子力委員はFNCAのビジョン・ステートメントと目標に立ち戻ることによりFNCAの基本精神を再確認した。 |
|
| |
| 2. |
日本の内閣府の永松荘一大臣官房審議官(科学技術政策担当)は前日開催された上級行政官会合(SOM)のサマリーを報告した。このサマリーレポートでは現行のFNCA協力プロジェクトの進展状況を紹介し、また「電子加速器利用」、「Tc-99mジェネレーター製造」、「バイオ肥料」、の3つの新プロジェクトにも焦点を当てた。これら3つの新プロジェクトは2001年の東京でのSOMで基本的に承認され、2002年からすでに活動を開始している。もうひとつの新プロジェクトである「アジアにおける持続的発展と原子力エネルギー」は第3回FNCA本会合の大臣級会合での最終承認を求めての報告があった。新プロジェクト「アジア原子力科学技術大学(AINST)」の提案に関しては、この提案を下記の「項目5」の下で要約された人材養成に関する円卓会合での討議を踏まえ、またIAEAが創設を計画している「国際原子力大学(INU)」にとくに顧慮を払い再検討すべきであるということで参加者は一致した。「海洋環境汚染研究」プロジェクトの提案は、RCA活動との重複を避けることを前提に支持された。この報告により、SOMのサマリー・レポートはMMで正式に採択された。 |
|
| |
| 3. |
FNCA各国は2002年10月31日午前のセッション1で自国のカントリー・レポートを発表した。このセッションでは、韓国の科学技術大臣と日本の原子力委員長が共同議長を務めた。各国の報告では自国で行なっている原子力研究開発の進展現況を含む平和利用原子力計画のさまざまの努力が、その国の政策の展開状況とともに紹介された。過去数年間のFNCA活動をレビューした後、本会合参加国は活動の目にみえる進展に感謝し、FNCA枠組内の今後の協力に注意を払った。これらのカントリー・レポートではさまざまな問題がカバーされた。引き続いての質疑応答、意見表明では次のトピックスがカバーされた。
| ・ |
原子力エネルギーはNPTの枠組内で厳正に平和目的に限って用いられるべきこととのFNCAのビジョン、また保障措置追加議定書の強化に関する日本での会合 |
| ・ |
北朝鮮の核兵器計画のニュースに関する懸念と、この問題の平和裏のまた可及的速やかな解決への強い希望 |
| ・ |
原子力損害賠償のための「アジア相互基金」 |
| ・ |
若い世代にとくに配慮した原子力知識の継承、その他の懸念事項 |
|
|
|
|
本会合では、さらに快適な環境におけるよりよい生活を求めてFNCA参加国が設定したFNCAの目標に則って、FNCA各国間で協力を促進することの重要性を各国代表は再確認した。 |
|
| |
| 4. |
午後のセッションでは、本会合にオブザーバーとして参加しているIAEAの代表(M.N.Razrey技術協力局アフリカ・東アジア太平洋課長)が「パートナーシップと技術統合による人類福祉の改善」に関する発表を行なった。Razrey氏はFNCA各国とくにアジア・太平洋地域に原子力技術が利益をもたらすためにIAEAが行なっているいくつかの努力を紹介した。 |
|
| |
| 5. |
円卓討議では、FNCA各国は「人材養成(HRD)戦略」と「持続可能な発展と原子力エネルギー」の2つのトピックスについて見解を表明し、コメントした。「HRD戦略」という最初のトピックは韓庚源(韓国原子力研究所(KAERI)原子力研修院長)が紹介した。同リードオフ・スピーカーは「第2の原子力ルネッサンス」の準備方策として原子力知識の継承の必要性を強調した。この見解は、ニーズ現況と運営とともに人材養成を促進するために継続した努力を払うべきなどのコメントに沿って、他の代表者のコンセンサスを得た。とくに以下の問題は重要と考えられた。 |
|
|
| ・ |
原子力知識の継承に関連した人材養成戦略に関する情報交換の促進 |
|
|
| ・ |
若い世代を原子力科学技術にひきつけるためのプログラムの開発 |
|
|
| ・ |
さまざまの技術分野の異なる関心の調和 |
|
|
| ・ |
将来的な国際原子力大学(INU)の設立準備のための、原子力技術分野の高等教育・訓練のためのアジアのネットワークの形成 |
|
|
| ・ |
人材養成のための他地域との協力や相互の働きかけ |
|
|
|
さらに、目的意識を明確にした方向性のもとに利用可能な人的資源と将来の資源ニーズに関する調査をFNCA各国で実施すべきと示唆があった。この調査によって人材養成戦略の開発のための貴重なデータが得られよう。さらに討議を続けて、人材養成のトピックのもとで可能な活動を検討するためのハイレベルなタスク・グループを設置することで合意した。 |
|
| |
| 6. |
もうひとつのトピックである「持続可能な発展と原子力エネルギー」は日本の遠藤哲也原子力委員長代理が円卓討議の紹介をした。遠藤委員長代理は、発電と非発電の両分野での原子力エネルギー利用が現代社会での持続可能な発展に果たす貢献についての評価を紹介した。またさらに原子力エネルギーを適切に用いることにより、「エネルギー安全保障(Energy
security)」、「環境保護(Environmental protection)」、「経済成長(Economic growth)」の3Eが達成できると紹介した。遠藤委員長代理のこういった見解に多くの各国代表は同意した。各国代表はエネルギー供給と持続可能な発展の密接な関連性を再認識した。多くの各国代表は現在も将来も原子力エネルギーがもっとも重要なエネルギー源のひとつであるとの見解を示した。クリーン・デベロプメント・メカニズム(CDM)と原子力エネルギーの関連性が討議され、提案されたプロジェクトを含むさらなるさまざまな研究が将来を考えるための足がかりになると認定された。 |
|
| |
| 7. |
第4回FNCA本会合は2003年秋に日本で開催する予定となっている。 |
|