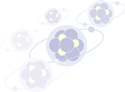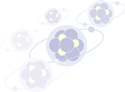
|
第6回 大臣級会合
FNCA9カ国の大臣級、人材養成プログラムで基本合意
 |
アジア原子力協力フォーラム(FNCA)に参加する9カ国の科学技術担当の大臣らが年に1度集うFNCA大臣級会合が2005年12月1日、東京において開催された。第6回となる今回は、円卓討議において「アジアにおける人材養成」と「科学技術と原子力」の2トピックスを取り上げた。同討議では、各国が持っている人材養成のニーズとプログラムを有機的に連携させるネットワーク作りに取り組むことで合意するとともに、原子力開発において国民の理解形成が重要であることやそのための日本の経験が紹介され、各国の経験や提案など活発な意見交換が行われた。 |
|
| 会合の参加者は日本をはじめ、オーストラリア、中国、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの 9 カ国。このほか、バングラデシュがオブザーバーとして初めて参加した。日本からは、松田科学技術政策担当大臣が首席代表を務めるとともに、近藤原子力委員長が議事全体を総括する議長を務めた。町原子力委員が FNCA 日本コーディネーターとして参加したほか、同委員会からは齋藤委員長代理と前田委員も参加した。 |
| <議事概要> |
 開会セッションにおいて、バングラデシュがオブザーバーとして参加することが全会一致で承認された。松田大臣は開会挨拶の中で、原子力安全の確保と核不拡散の担保を大前提に、放射線利用の進展への期待と原子力エネルギーの役割の重要性を強調した。同大臣はまた、核不拡散体制の維持・強化の必要性を述べるとともに、 FNCA 参加国のうち、追加議定書の未締結国に対し早期締結を呼びかけた。 開会セッションにおいて、バングラデシュがオブザーバーとして参加することが全会一致で承認された。松田大臣は開会挨拶の中で、原子力安全の確保と核不拡散の担保を大前提に、放射線利用の進展への期待と原子力エネルギーの役割の重要性を強調した。同大臣はまた、核不拡散体制の維持・強化の必要性を述べるとともに、 FNCA 参加国のうち、追加議定書の未締結国に対し早期締結を呼びかけた。 |
セッション2においては、各国代表によりそれぞれの原子力研究開発政策とFNCA活動状況について報告が行われた。各国とも、放射線利用分野における着実な成果を確認し、FNCA参加国間の一層の協力促進が重要であることを強調した。また、多くの国が地球温暖化問題への対応やエネルギー安定供給の確保を図る上で、原子力エネルギー利用の重要性を再認識した。
セッション3の円卓討議は、各国代表による政策対話の場として「アジアにおける人材養成」と「科学技術と原子力」の2テーマが取り上げられた。議論の概要は以下のとおり。
「アジアにおける人材養成」
前回会合においてベトナムから提案された「アジア原子力大学(ANU)」構想を、FNCAの人材養成プロジェクトや上級行政官会合(SOM)において審議した経緯が本討議に報告された。報告によると、ANUは「アジア原子力教育訓練プログラム(ANTEP)」と改名され、FNCA参加各国の既存の人材養成基盤を有効に活用するための有機的な連携ネットワークとなった。この報告を基に、その基本構想や各国の参加や貢献のコミットメント、今後の具体的な進め方とスケジュールについて合意が得られた。それによると、各国コーディネーターは2006年1月を目途に各国の人材養成のニーズと貢献できるプログラムを事務局まで提出し、3月のコーディネーター会合において具体的な実施方法を議論し、その結果を次回の大臣級会合に報告する。
「科学技術と原子力」
松田大臣が冒頭、リードオフスピーチを行い、参加各国の高い評価を受けた。日本が原子力に関する国民の理解を得るために行った経験に対し、各国は高い関心を示し、さまざまな提案や経験が議論された。同大臣は、アジア各国の科学技術政策担当大臣による政策対話の重要性について触れ、複数の代表がこの考えに賛意を表明した。
最後に、本会合のサマリーがとりまとめられると同時に、次回会合は2006年にマレーシアにて開催されることが確認された。 |
|
<添付資料>
第6回FNCA大臣級会合 プログラム
同 参加者名簿
同 サマリー
|
|