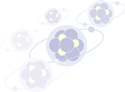アジア原子力協力フォーラム(FNCA)
第8回大臣級会合
概要
2007年12月18日(火)、東京(三田共用会議所)
内閣府・原子力委員会主催により、第8回FNCA大臣級会合が2007年12月18日(火)、東京(三田共用会議所)において開催された。FNCA参加国であるオーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの全10ヶ国から原子力を所管する大臣級代表が出席した。
 我が国からは、岸田内閣府特命担当大臣(科学技術政策)が会合議長として参加するとともに、近藤原子力委員会委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員及び内閣府原子力政策担当室丸山室長、西川次長をはじめ、文部科学省、外務省、経済産業省の担当官並びに、町FNCA日本コーディネーターが参加した。 我が国からは、岸田内閣府特命担当大臣(科学技術政策)が会合議長として参加するとともに、近藤原子力委員会委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員及び内閣府原子力政策担当室丸山室長、西川次長をはじめ、文部科学省、外務省、経済産業省の担当官並びに、町FNCA日本コーディネーターが参加した。
会合では、2007年度のFNCA活動の報告や、今後のFNCA活動に対する討議、さらには「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するFNCA共同コミュニケ(別添1)」の署名式等が行われた。
 共同コミュニケは、(1)2013年以降の地球温暖化対策の枠組みにおいて、原子力発電の導入を促進し、原子力発電をクリーン開発メカニズム(CDM)等の対象とすべきこと、また、(2)原子力発電の利用は、核不拡散、原子力安全、核セキュリティの確保が大前提である旨について再確認し、地域として今後協力して取り組みを行っていくこととしている。地域としてこのような共同コミュニケを発出したのは世界でも初めてであり、大変意義あることであり、今後、共同コミュニケのメッセージは、地球環境問題が話し合われる国際会議等において発信していくこととなった。 共同コミュニケは、(1)2013年以降の地球温暖化対策の枠組みにおいて、原子力発電の導入を促進し、原子力発電をクリーン開発メカニズム(CDM)等の対象とすべきこと、また、(2)原子力発電の利用は、核不拡散、原子力安全、核セキュリティの確保が大前提である旨について再確認し、地域として今後協力して取り組みを行っていくこととしている。地域としてこのような共同コミュニケを発出したのは世界でも初めてであり、大変意義あることであり、今後、共同コミュニケのメッセージは、地球環境問題が話し合われる国際会議等において発信していくこととなった。
セッション毎の会合概要は次の通り。
開会セッション
冒頭、セッション議長である近藤原子力委員長によって、本会合の開催によせた福田総理大臣からのメッセージが読み上げられた。続いて、岸田大臣が開会挨拶を行い、原子力発電の促進を目標とした協力を実施し、農業や医学などへの放射線利用の推進においても多くの成果をあげつつあるFNCAの活動は、アジア地域の持続的発展に貢献するものであり、ますます重要性を増していることを述べた。次に、参加各国代表の自己紹介が行われた。
その後、西川次長より、上級行政官会合の議長として、前日開催された同会合において「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するFNCA共同コミュニケ(案)」及びFNCA活動に関する「第8回FNCA大臣級会合決議(案)」がとりまとめられ、大臣級会合に提案することになった旨の報告がなされた。
セッション1:FNCA活動報告
町FNCA日本コーディネーターより、 第8回コーディネーター会合(2007年3月開催)の結果と、8分野(研究炉利用、農業利用、医学利用、工業利用、放射線廃棄物管理、原子力広報、原子力安全文化、人材養成)におけるプロジェクトの成果、及び 第8回コーディネーター会合(2007年3月開催)の結果と、8分野(研究炉利用、農業利用、医学利用、工業利用、放射線廃棄物管理、原子力広報、原子力安全文化、人材養成)におけるプロジェクトの成果、及び 第1回「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル(2007年10月開催)」の結果について報告がなされた。また、今後の検討課題として、地域や各国のプライオリティのより的確な反映、成果の利用に関する最終ユーザーとの協力の強化、他の地域協力活動との協同による効率化等が提案された。 第1回「アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル(2007年10月開催)」の結果について報告がなされた。また、今後の検討課題として、地域や各国のプライオリティのより的確な反映、成果の利用に関する最終ユーザーとの協力の強化、他の地域協力活動との協同による効率化等が提案された。
セッション2:原子力エネルギーの平和利用への取組みとFNCA活動
各国の代表より、原子力エネルギーに係わる政策全般、原子力発電の利用と関連する活動の状況及び各国のFNCA活動への取組について報告された。日本からは近藤原子力委員長が報告を行った。
【各国発表概要】
 |
バングラデシュ |
|
| |
エネルギー面では、国民の35%のみが電力を利用している状況であり全国民が電力の利用を可能とすることが課題。また、干ばつ・洪水などCO2の排出削減が重要と認識。将来のエネルギー需要を満たすためにも原子力発電について検討。非発電分野では、ガン治療が大きな課題。 |
 |
 |
中国 |
|
| |
国家政策として環境保護を重視。原子力発電を含む再生利用エネルギーを促進。原子力技術開発については、高温ガス炉、GIF(第4世代原子力システムに関する国際フォーラム)、ITER(国際熱核融合実験炉)など国際協力に積極的に参画するとともに、放射性廃棄物の管理など規制体制を強化。 |
 |
 |
インドネシア |
|
| |
放射線育種、テクネチウム99mジェネレータなどFNCAの放射線利用分野での成果を活用。医療分野も含め今度もFNCA活動に積極参画。エネルギー安定供給のため、原子力発電を必要としており、安全を確保し2015年―2019年に原子力発電の運転開始に向け取組む。 |
 |
 |
日本 |
|
| |
原子力政策大綱に則り平和利用に限定し原子力を促進、FBR(高速増殖炉)及び先進軽水炉などの開発を進めている。柏崎刈羽原子力発電所における地震による経験を国際社会と共有することが重要。原子力発電の新規導入国の人材養成など基盤整備をサポート。放射線利用分野の促進、ANTEP(アジア原子力教育訓練プログラム)の促進も重要。パートナーシップの精神のもと協力を促進。 |
 |
 |
韓国 |
|
| |
エネルギーの確保が第一の優先課題であり原子力発電は第一のオプション。2007年1月に第3次包括的原子力推進計画を策定するとともに廃棄物保管場を決定。INPRO(革新的原子炉及び核燃料サイクルに関する国際プロジェクト)、GIF(第4世代原子力システムに関する国際フォーラム)、GNEP(国際原子力エネルギー・パートナーシップ)などの国際協力に積極的に参画。IAEAによるNuclear Safety Schoolの役割は重要。原子力エネルギーについてのFNCAの協力に積極的に貢献。 |
 |
 |
マレーシア |
|
| |
原子力発電の導入は決定していないが、原子力の安全・不拡散にかかわる様々な国際条約を締結、それに沿って法整備を進めるとともに原子力の広報活動に注力。ANTEP(アジア原子力教育訓練プログラム)の下での人材育成を推進し、FNCA活動に積極的に参加するとともに、特に医療分野に注力を表明。 |
 |
 |
フィリピン |
|
| |
2007年初めにエネルギー省が原子力発電を電力供給のオプションとして見直しを開始。国内では原子力関連のセミナー等を開催。また、閉鎖中の原子力発電所(バターン)の復活に向けた調査が始動。2007年1月の第2回東アジアサミット、同年8月の第25回ASEANエネルギー大臣会合でエネルギー供給の1つとして原子力に言及。特に後者では、ASEAN原子力安全サブセクターネットワーク設立を合意。 |
 |
 |
タイ |
|
| |
輸入エネルギー依存やエネルギー消費の増加、石油価格高騰等から原子力発電の導入を計画。国家エネルギー政策評議会や国家エネルギー政策委員会、内閣がタイ国家エネルギー政策や開発計画を承認。2020年−2021年に4,000MWの原子力発電所導入を計画。現在建設サイトを選定中。今までのFNCA活動に感謝しつつ、放射線加工の分野でFNCAとRCA(原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定)の協力に期待。 |
 |
 |
ベトナム |
|
| |
2006年1月に、2020年までに最初の原子力発電所の建設、運転を行うとの「原子力エネルギーの平和利用のための長期戦略」を策定し、2007年7月に同長期戦略を実行するための「行動計画」を策定するとともに「原子力法」の制定に向け作業中。不拡散・原子力安全・核セキュリティの確保にコミット。原子力発電にかかわる情報共有に期待。従来のFNCAの活動分野においても継続して協力を推進。 |
 |
 |
オーストラリア |
|
| |
2007年11月に政権が交代、原子力発電は支持しないもののウラン採掘は継続して支持。バリの第13回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP13)にて京都議定書に批准。原子力発電の将来の取組みは見えないが、放射性廃棄物の安全処理、オパール炉のような原子力科学技術については今後も継続して取り組む。RCAとの相乗効果及びプロジェクトを適切に評価し効率的に推進することを期待。 |
 |



セッション3:放射線利用を中心としたFNCA活動
町末男FNCA日本コーディネーターより、放射線利用分野である研究炉利用、農業利用、医学利用、工業利用分野の成果と今後の取り組みの方向について、テクネチウム99mジェネレータ等の例を挙げ報告された。
セッション4:円卓討議:FNCAの今後の活動
西川次長より、 2008年度FNCA計画、 2008年度FNCA計画、 共同コミュニケの内容とその積極的発信、 共同コミュニケの内容とその積極的発信、 「第1回アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」のフォローアップ等、今後のFNCA活動計画等について上級行政官会合としての提案を説明。その後参加者により「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するFNCA共同コミュニケ(別添I)」及びFNCA活動に関する「第8回FNCA大臣級会合決議(別添II)」に関し活発な意見交換が行われ、合意を得た。 「第1回アジアの原子力発電分野における協力に関する検討パネル」のフォローアップ等、今後のFNCA活動計画等について上級行政官会合としての提案を説明。その後参加者により「持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するFNCA共同コミュニケ(別添I)」及びFNCA活動に関する「第8回FNCA大臣級会合決議(別添II)」に関し活発な意見交換が行われ、合意を得た。
閉会セッション
閉会セッションでは、岸田大臣より会合サマリー案が報告され各国から了承された。
引き続き、9ヶ国−日本、バングラデシュ、中国、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの代表が共同コミュニケに署名を行った。署名にあたっては、岸田大臣を始め各国代表から、本コミュニケは、エネルギー安定供給と地球温暖化対策としての原子力発電の活用を地域ブロックから提案した画期的なものであること、今後コミュニケにうたわれた理念を具体的な行動に移すことが重要であり核不拡散・原子力安全・核セキュリティを確保した原子力発電の促進に協力して取組むべきこと、等の所感が述べられた。
署名後に参加10ヶ国による共同記者会見を実施した。冒頭、岸田大臣から本会合の結果概要が紹介されるとともに、共同コミュニケの意義について述べられた。その後、質疑応答の中で、岸田大臣より、共同コミュニケのメッセージは、地球環境問題が話し合われる国際会議等において積極的に発信していく等の意図表明がなされた。
最後に、エステラ・F・アラバストロ、フィリピン科学技術大臣より、第9回FNCA大臣級会合がフィリピンで開催されることが紹介された後、岸田大臣より閉会が宣言された。
別添:
- 持続的発展に向けた原子力エネルギーの平和利用に関するFNCA共同コミュニケ
- 第8回FNCA大臣級会合決議
|